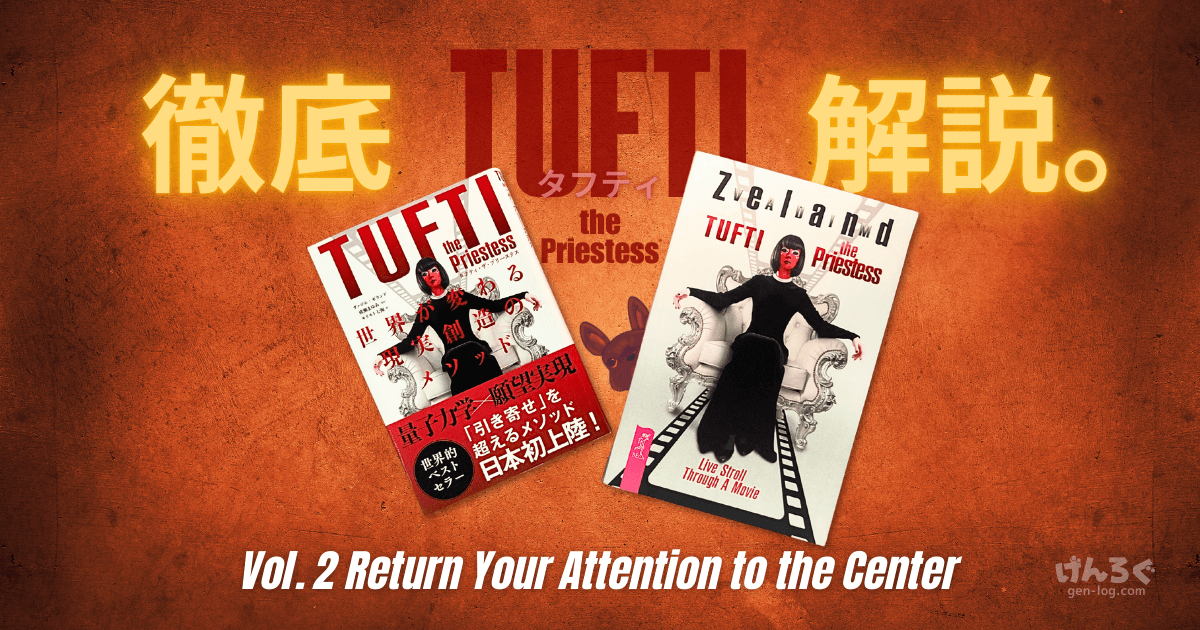気づきの中心点はどこにあるのか?
「引き寄せ」を超える現実創造のメソッドとして、各方面で大注目の一冊、
タフティ・ザ・プリーステス
世界が変わる現実創造のメソッド
この難解なタフティの理論を、英語版TUFTIも交えながら、どこよりもわかりやすい解説を目指してお届けするタフティ徹底解説シリーズ。
第2弾の今回は、
気づきの中心点
というワードについて深掘りしたいと思います。
それでは、始めていきましょう。
気づきの中心点
現実の中で目覚めるにはどうすればいいのでしょうか?
起きているときに目覚めるためには、意識の向け先に注意する必要がある、とタフティは言います。
ポイントは3つ
- 気づきの中心点に意識を向ける
- 自分を見て、現実を見る
- 外部トリガーと内部トリガー
詳しく解説していきます。
気づきの中心点とは
本書の中で繰り返し出てくるのが、
気づきの中心点に意識を向ける
という表現です。
初見だと全く意味がわからないかと思いますが、このメソッドのキーとなるテクニックなので、しっかり理解する必要があります。
外部スクリーンと内部スクリーン
私たちは、この世界を外部スクリーン・内部スクリーンという2つのスクリーンを通して見ています。
- 外部スクリーン
- 外側で起こっている出来事を知覚している時、またはそれに反応している時
- 内部スクリーン
- 心の中の感情や頭の中の思考に意識が向いている時
我々は通常、この2つのスクリーンのいずれかに意識が向いている状態ですが、その状態でいるとき、あなたは眠りに落ちています。
例えば、あなたが道を歩きながら将来のことについて思い悩んでいるとします。
この時、あなたは内側の感情や思考に意識が向いている状態なので、
- 前からどんな車が来たのか
- どんな人とすれ違ったのか
という外的な情報には一切意識が向いていません。
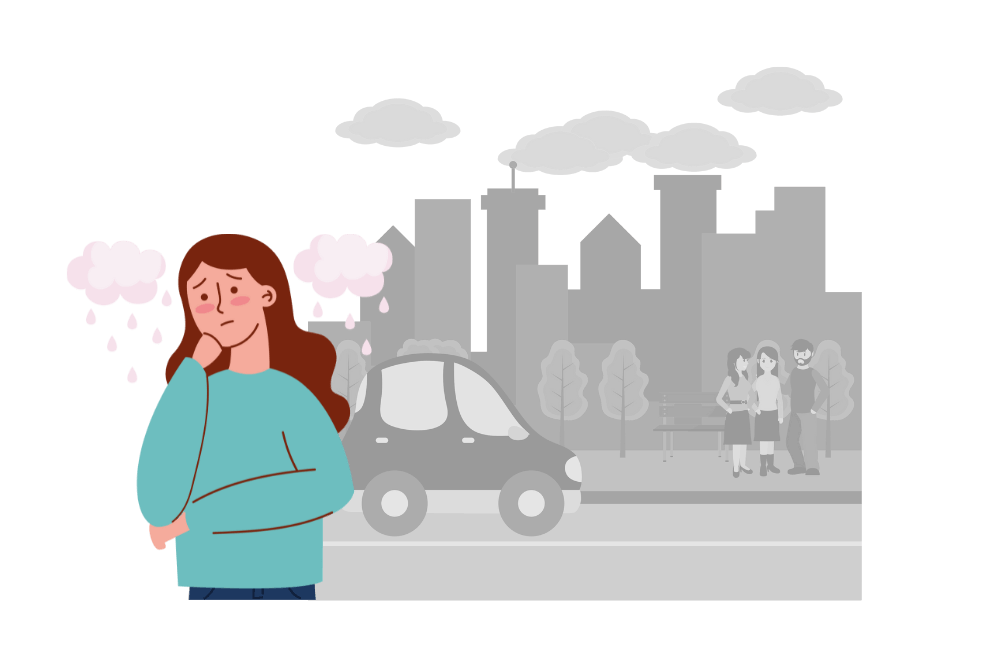
そこで、突然目の前で轢き逃げ事故が発生したとします。
すると、あなたはパニックになりながらも、なんとかこの場の対処にあたろうとします。
そうすると、今まで考え込んでいた将来への不安(内部スクリーン)から、今外側の世界で起こっているアクシデント(外部スクリーン)に意識の向け先が移動し、
- 加害者の車のナンバーや車種
- 被害者の怪我の状態
などの外的な情報を必死にかき集めようとします。
この時、今目の前で起こっていることの対処に追われているため、ついさっきまで頭をいっぱいにしていた将来への不安は全く意識に上っていない状態です。
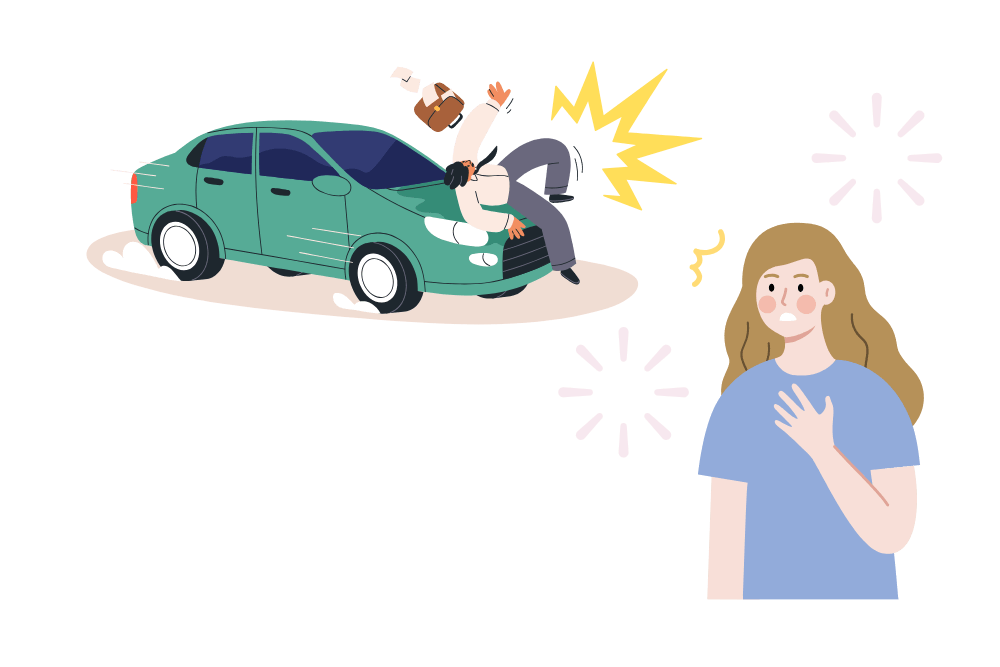
気づきの中心点はどこにもない
しかし、どちらも台本通りに動かされている状態、すなわち眠りに落ちている状態ということになります。
ここで、意識の視座を上げて、完全な観察者としてこの世界を俯瞰している状態になると、あなたの意識は気づきの中心点に移動し、現実の中で目覚めることができます。
つまり、気づきの中心点とは、内と外のどちらのスクリーンにもフラットに意識が向いている状態のことです。
したがって、気づきの中心点とはどこか身体的な場所を示しているのではなく、意識の置き所を示したものであるため、
 げん丸
げん丸気づきの中心点ってどこ?
と、具体的な場所を探そうとしても見つかりません。
本書での表現についての見解
ちなみに本書では、
夢や現実の世界で目を覚ますためには、内と外のスクリーンから意識をそらし、「気づきの中心点」に意識を向けなければなりません。
タフティ・ザ・プリーステス 世界が変わる現実創造のメソッド P15
とありますが、私の感覚では、「意識をそらす」という表現はあまりしっくり来ていません。
なぜなら、あなたの意識が気づきの中心点にいるとき、あなたは内と外のスクリーンを同時に見ており、意識をそらすとは真逆の状態だからです。
また、スクリーンは内と外の2つしかないので、そもそも意識をそらす先がありません。
この点に関しては、英語版の表現の方がしっくり来ます。
To wake up in a dream or waking reality, you must pull your attention away from the inner and outer screen and shift it to your awareness centre.
TUFTI the Priestess, P10
pull your attention away
とあるので、意識をそらすというよりは、どちらかのスクリーンに入りすぎている意識を引き離す、中心まで引き上げるというイメージです。
つまり、意識の方向を変えるのではなく、今いる意識状態から一歩引いて、全体として映像を見るという感覚です。
さらに言うと、
- 「気づきの中心点」に意識を向ける
ではなく、
- 「気づきの中心点」から内と外のスクリーンに意識を向ける
という感覚が近いのではないでしょうか。
しかしながら、当ブログでは便宜上「気づきの中心点に意識を向ける」という本書での表現を踏襲しています。
現実の中での視点の違いについては、
の記事を読んでいただけると、より理解が深まるかと思います。
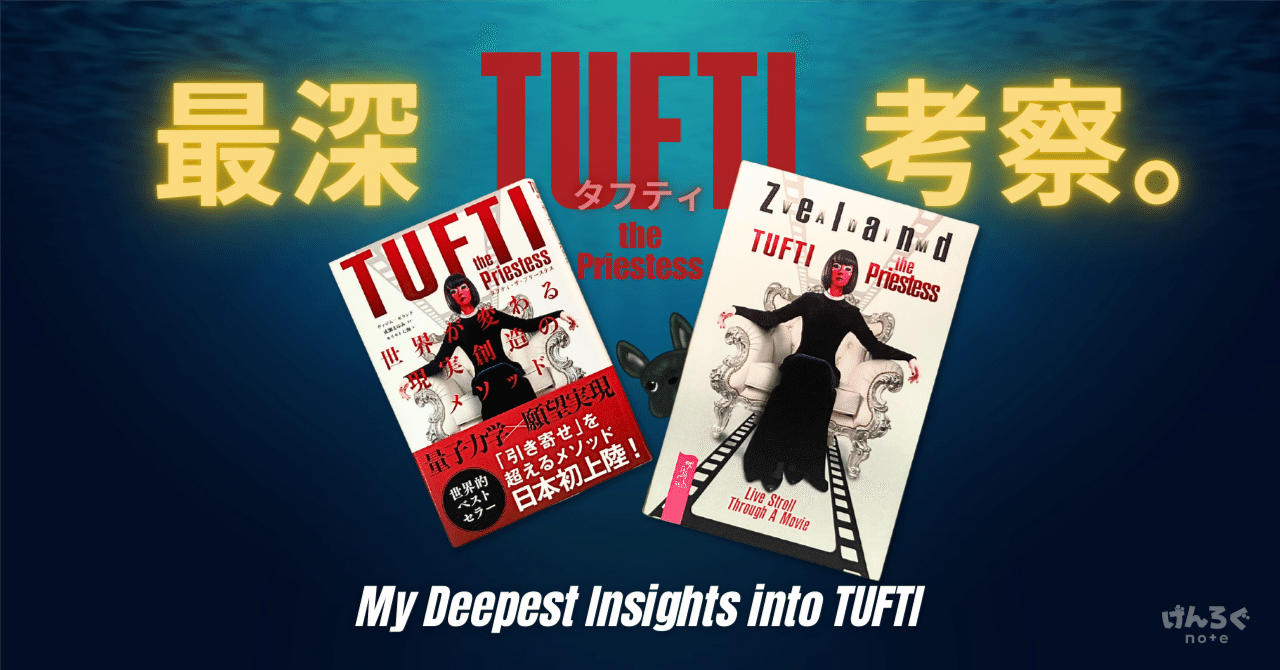
自分を見て、現実を見る
では、どうすれば気づきの中心点に意識を戻せるのでしょうか?
本書のテーマが「気づきの中心点に意識を向ける」であるならば、本書のキャッチフレーズと言えるのがこちら、
自分を見て、現実を見る
このフレーズが、タフティのメソッド全体の基本姿勢になるので、しっかりと理解していきましょう。
「見る」の正しい認識
「見る」というのは、外側から観客として「現実」という映画を見るということです。
つまり、どちらのスクリーンの中にも入らず、その間から2つのスクリーンを同時に見ている状態です。
もう少し噛み砕いて言うと、自分の内側で湧き起こる感情や、外側で起こった事象に対して、一切のジャッジメントをせずに、ただの現象としてフラットに認識している状態です。
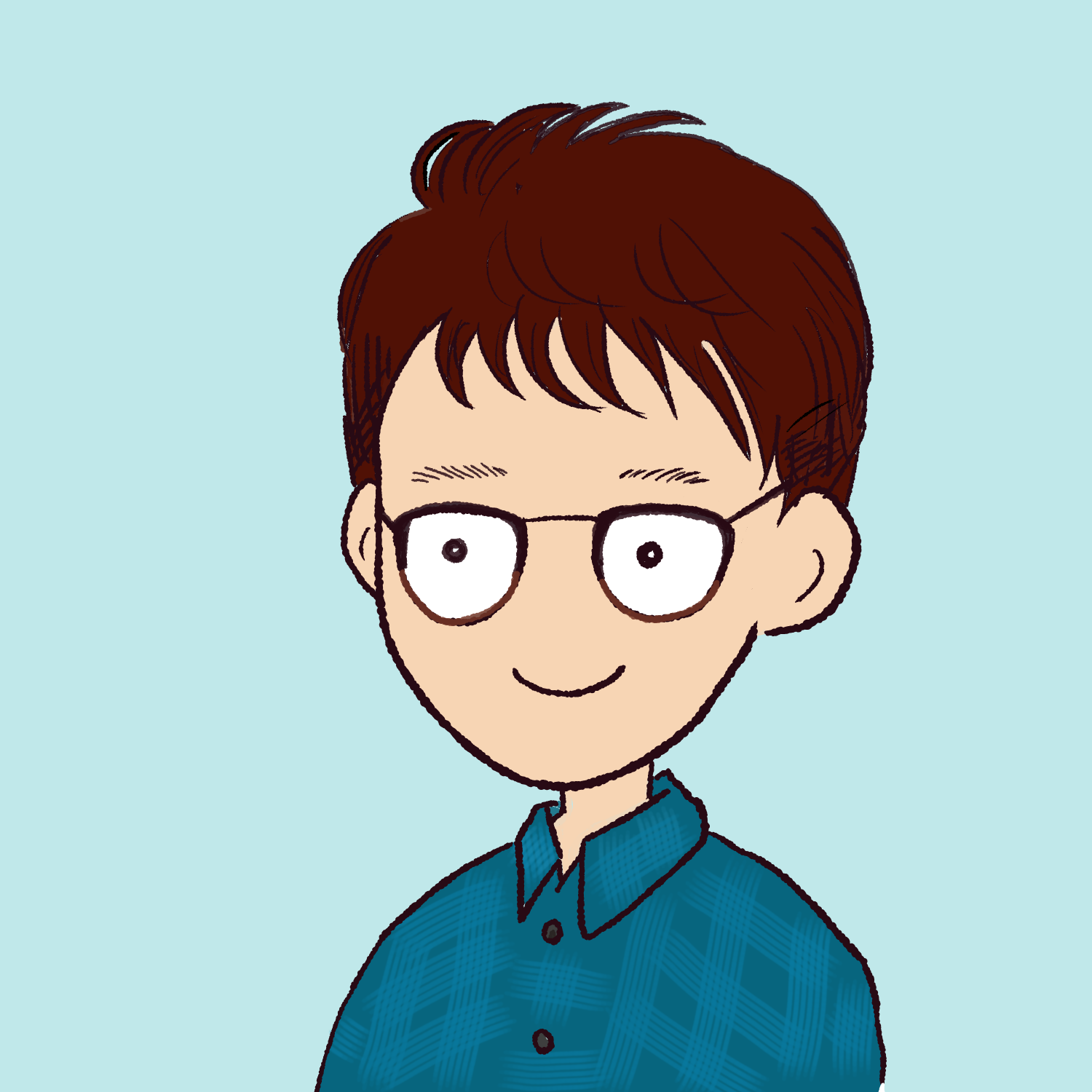 えいじ
えいじ瞑想でいうと、マインドフルネスと内観のちょうど間のポジションをキープするようなイメージかな
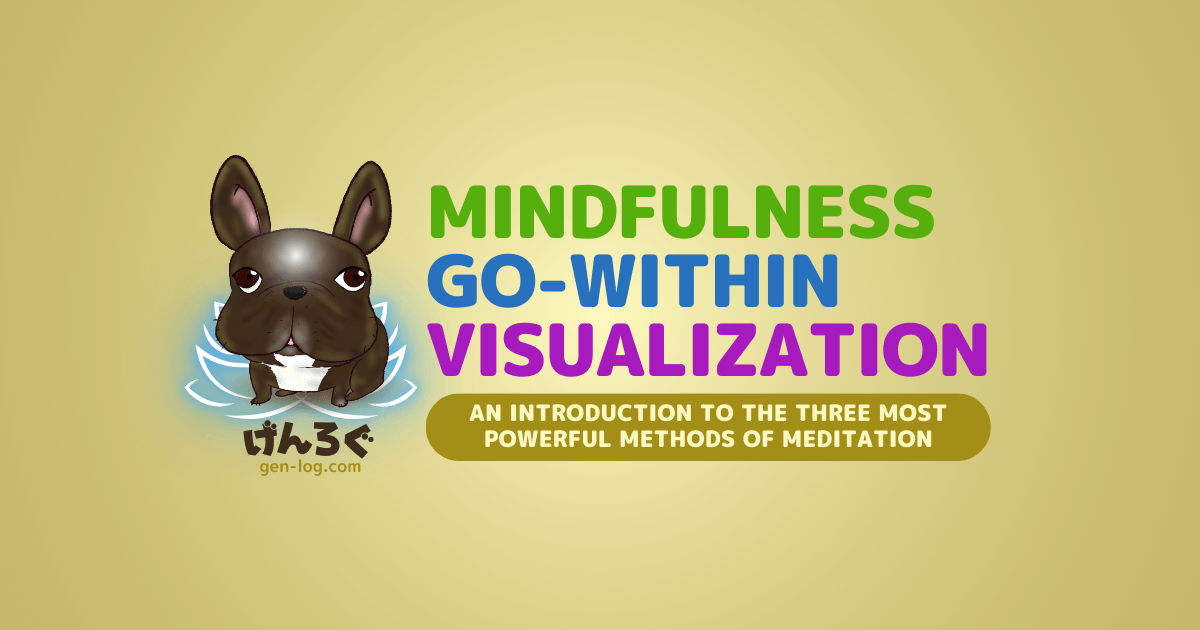
「見る」と意識した瞬間に、その事象や感情はあなたの意識の外で起こっていることになります。
なぜなら、あなたの意識がそのスクリーンの中にいる時は、それらを「見る」ことができないからです。
現実をスクリーンの映像として「見る」
この「見る」というのは、物理的に目で見るということではなく、起こっている事象や感情をスクリーンに映し出された映像として見るということです。
例えば、あなたが映画を見ているとします。
あなたはスクリーンの中で起こっていることに対して、驚いたり、ドキドキしたりします。
あるいは、登場人物に感情移入して、涙を流すこともあるでしょう。
しかし、あなたはそのスクリーンの中で起こっていることはリアルではないと知っているので、色々な感情の変化はありながらも、常に俯瞰して、エンタメとしてその作品を「見て」いる状態です。
同じことを、この「現実」という映画でも行うのです。
先ほどの交通事故の例で説明すると、
- 道を歩きながら将来の不安で頭がいっぱいになっている自分を外側から「見る」
- 目の前で事故が起こってパニックになっている自分を外側から「見る」
- 事故の惨劇をただの映像として客観的に「見る」
といった感じです。
あなたが眠っている時も、目を覚ましている時も、あなたの内側や外側で起こっていることは、現実として起こっているということに変わりはありません。
しかし、意識の向け先に注意すると、その事象に対するあなたの意識の位置や距離感が変わります。
この感覚がわかると、「自分を見て、現実を見る」の意図が掴めるかと思います。
So, get into the observation point telling yourself: I see myself and I see reality.
TUFTI the Priestess, P13
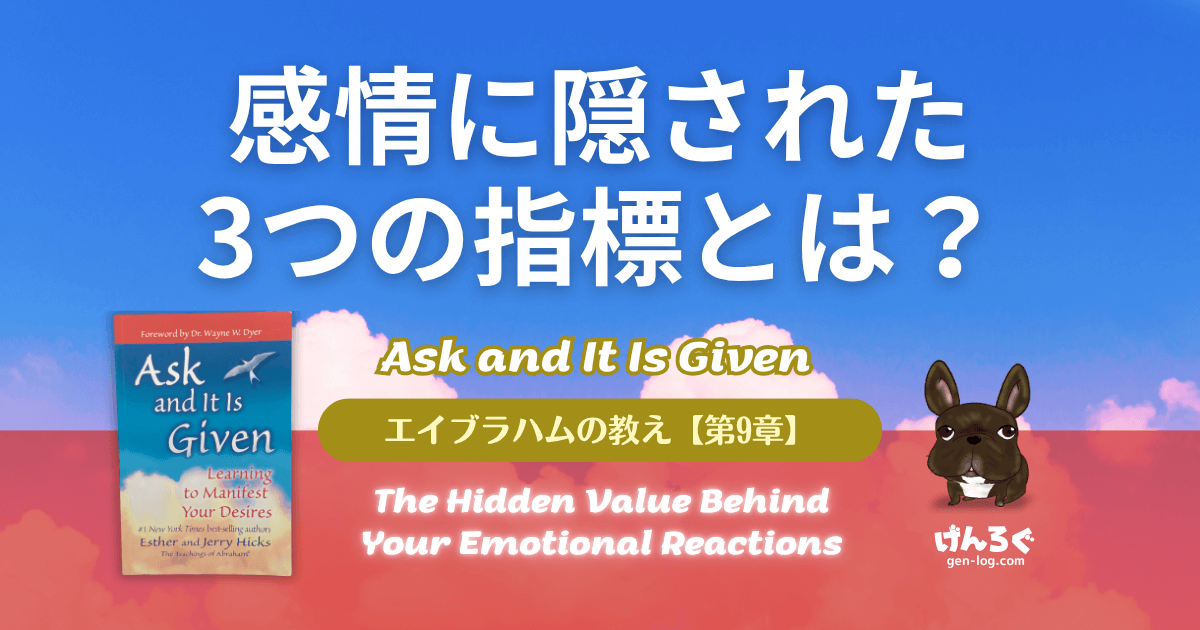
外部トリガーと内部トリガー
気づきの中心点に意識を戻すコツはあるのでしょうか?
我々は普段、外側で何かが起こると、
- その出来事に対して意識を向ける
- その出来事によって発生した不安や心配に意識を向ける
という反応を習慣的に見せますが、この反応を見せた時、あなたは眠りに落ちます。
そのため、気づきの中心点に留まる技術を習得するには、これと逆の習慣を身につける必要があります。
今までは何かが起こると眠っていたところを、今度はそれを目を覚ますシグナルだと思う癖をつけるのです。
意識の向け先をどこにするかを思い出すためのトリガー(きっかけ)は2つあります。
- 外部トリガー
- 何かが起きれば、目を覚ます
- 内部トリガー
- 何かをする前に、目を覚ます
外部トリガー
例えば、外部トリガーの場合、
- 誰かに会う
- 誰かに頼み事をされる
- 何かの音がする
- 何かが動く
といった外的なイベントが起こったら、すぐに意識を中心点に持っていくようにします。
たとえ無意識に反応してしまったとしても、なるべく早く中心点に戻るように心がけて、コントロールを失わないようにします。
内部トリガー
次に、内部トリガーの場合ですが、
- どこかに出かけようとする
- 何かをしようとする
- 誰かと話そうとする
といった自発的な行動を起こす前に、意識を中心点に戻します。
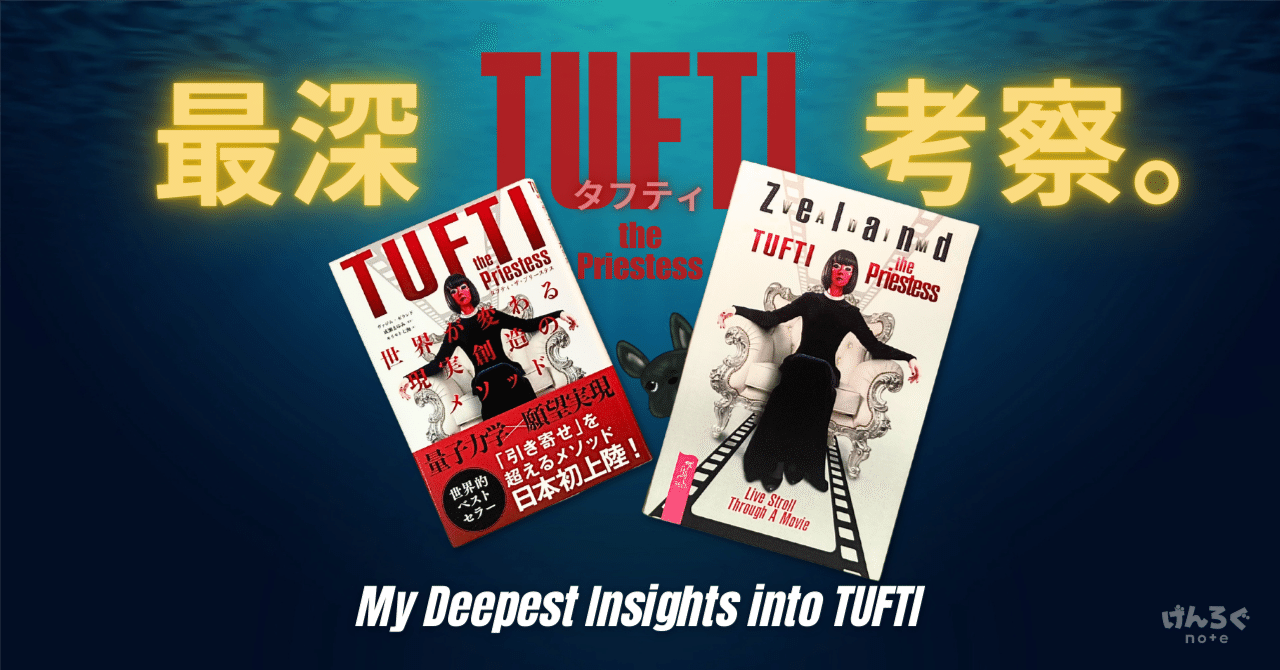
中心点に意識を留めることの意義
また、意識を気付きの中心点に留めるというのは、
- 世の中を達観して何も感じなくする
- 起こった現実を非現実的に捉える
ということではありません。
これは、現実に対しての臨場感はそのままに、起こった現実に対する視点を変えるという感覚です。
それゆえ、この練習の真の目的は、いかに長く中心点に留まるかということではなく、起きている出来事に対する対応力を磨くというところにあります。
There is no need to try and hold your attention at the centre all the time without taking a break. The meaning and value of this exercise lie in something else: your ability to respond to what is happening.
TUFTI the Priestess, P20
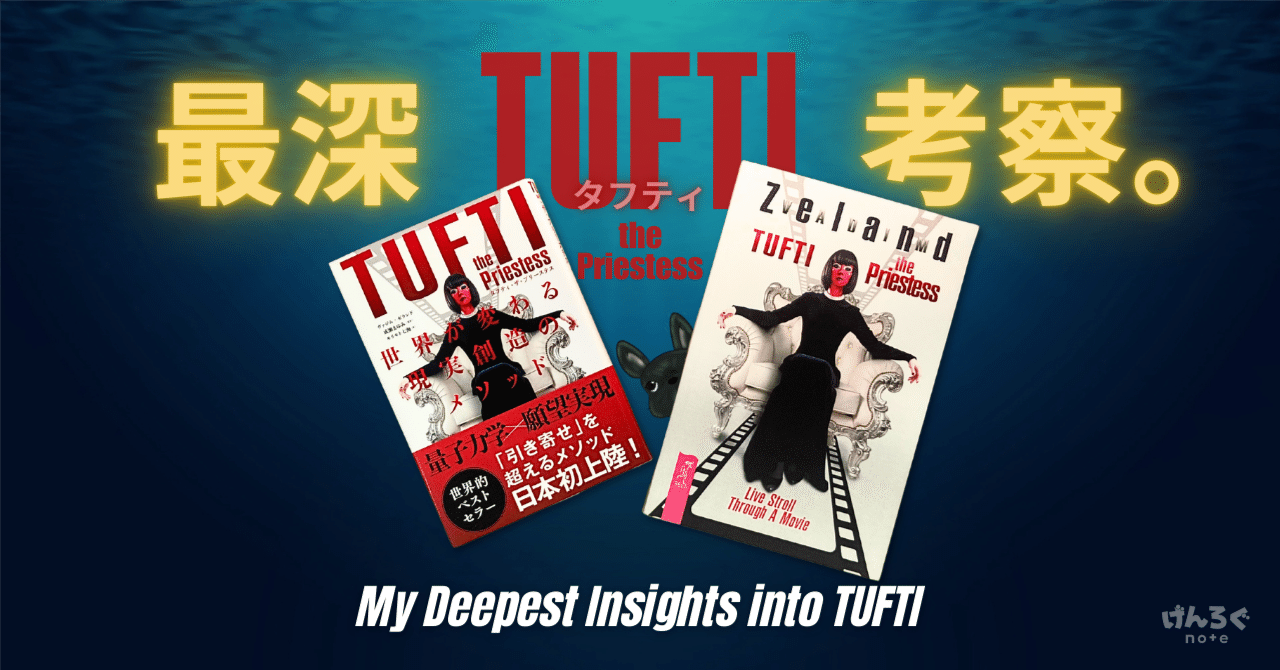
まとめ
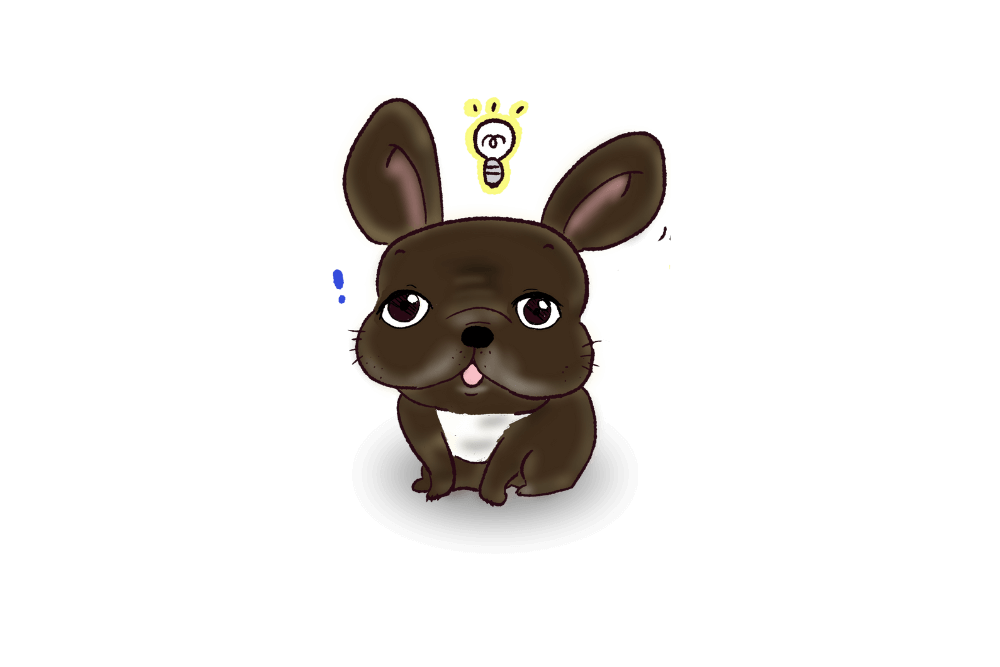
- 気づきの中心点とは、外部スクリーン・内部スクリーンのどちらにもフラットに意識が向いている状態のこと
- 気づきの中心点に意識を戻す合言葉は「自分を見て、現実を見る」
- 「何かが起きれば、目を覚ます」「何かをする前に、目を覚ます」という癖をつける
- いかに長く中心点に留まるかではなく、起こったことに対する対応力を磨くことが重要
あなたが気づきの中心点にいるとき、内と外のどちらのスクリーンにも意識が向いている状態だと説明しました。
しかし、矛盾しているようですが、どちらのスクリーンも意識していない状態とも言うことができます。
この場合の「意識していない」とは「認識していない」や「無視をする」という意味ではありません。
意識がその出来事やそれに対する感情を認識しつつも、意識がそのことについて囚われていない状態ということです。
むしろ、気づきの中心点にいるときは、非常に冷静で客観的な視点から見ることになるので、どちらかに囚われている時よりも全体がよりクリアに見渡せるようになります。
もう少し俗っぽい表現にすると、この現実世界を超高精細で超リアルな感覚を伴ったVRゲームだと思って、一人称視点からキャラクターを操作する感覚に近いでしょうか。
 げん丸
げん丸まさにマトリックスの世界観ブヒな!
そして、「自分を見て、現実を見る」というのは、その中心点に戻るための武道の型のようなものです。
- 何かが起きれば、「自分を見て、現実を見る」と目を覚ます
- 何かをする前に、「自分を見て、現実を見る」と目を覚ます
という訓練を日頃からしていれば、不意に起こった状況の中でも、すぐに目覚めるための合言葉として、
 えいじ
えいじ自分を見て、現実を見る…
と心で唱えることによって、理屈抜きで意識を一瞬で中心に戻すことができるようになります。
これからタフティの実践的なメソッドを学ぶにあたり、この「気付きの中心点に意識を戻す」というのは基本の動作になるので、ぜひマスターしていただければと思います。
それではまた、次の記事でお会いしましょう。
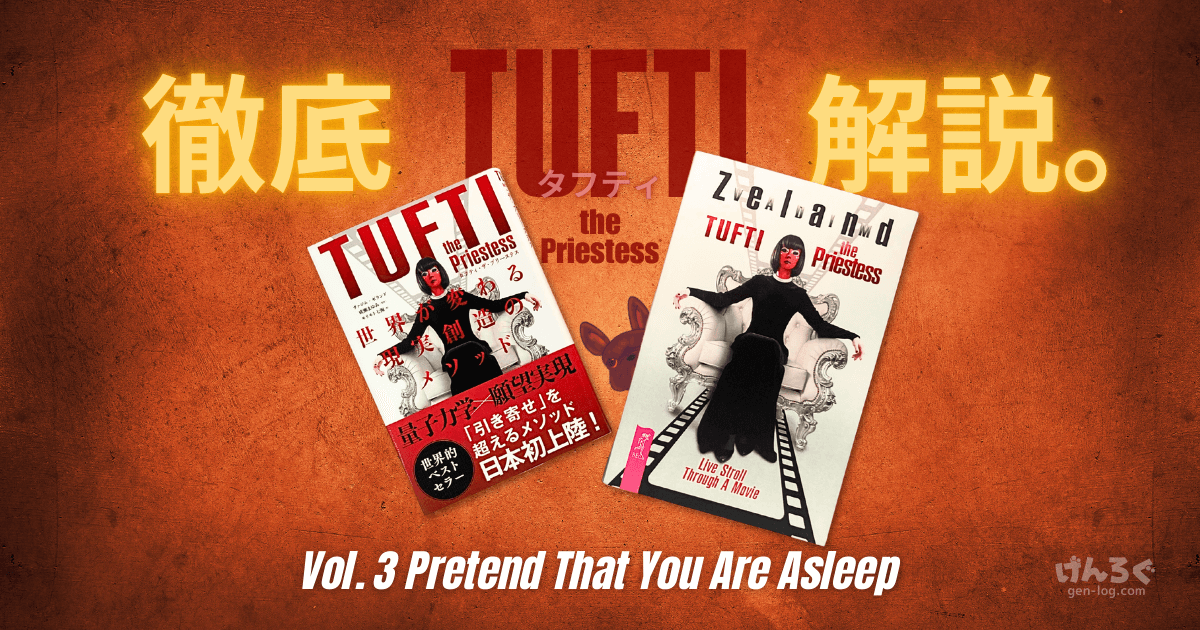
タフティの著者によるトランサーフィン実践書
一発でオーダー完了—究極の引き寄せメソッド
引き寄せの法則の元祖—エイブラハムの教え
絶対に現実を変えたい…
という人へ
現実を好転させるには、
まず魂の声を聞いてあげよう
願望実現において、ベースとなるのは今のあなたの状態です。
いくら、アファメーションやイメージングで、ワクワクを感じようとしても、今のあなたが傷ついている状態では、あなたは強い抵抗を感じてしまうでしょう。
多くの願望実現のメンターたちは、
現実は無視!
願いが叶っている自分だけに集中!
と、口を揃えて言いますが、無視していいのは「現実」という幻想だけです。
それは、あなたの魂の声を無視するということでは決してありません。
現実創造には、
- カルマ
- 過去世・前世
- 宿命・運命
- 使命・ミッション
- ツインレイプログラム
といった、さまざまな条件が絡み合っており、特に宇宙由来の魂を持つスターシードやライトワーカーの人たちは、説明できない生きづらさや物質世界に対する違和感を感じています。
そのような人たちは、魂レベルでのブロックが何層にも重なっている可能性があるので、自分の魂のルーツを知るということが非常に有効になります。
私は以前、人生に行き詰まった時、ココナラというプラットフォームで鑑定を受けてから、急に道が開けるような体験をしました。
- 現実を変えようと行動すると、ひどい揺り戻しに遭う
- 逆らえない大きな力の流れを感じる
- 何かに強力に導かれているような気がする
- あり得ないシンクロニシティが頻発する
といった自覚がある方は、こちらの記事を読んでいただくと、状況を打開するきっかけになるかもしれません。
— 実際にセッションを受けた体験談 —