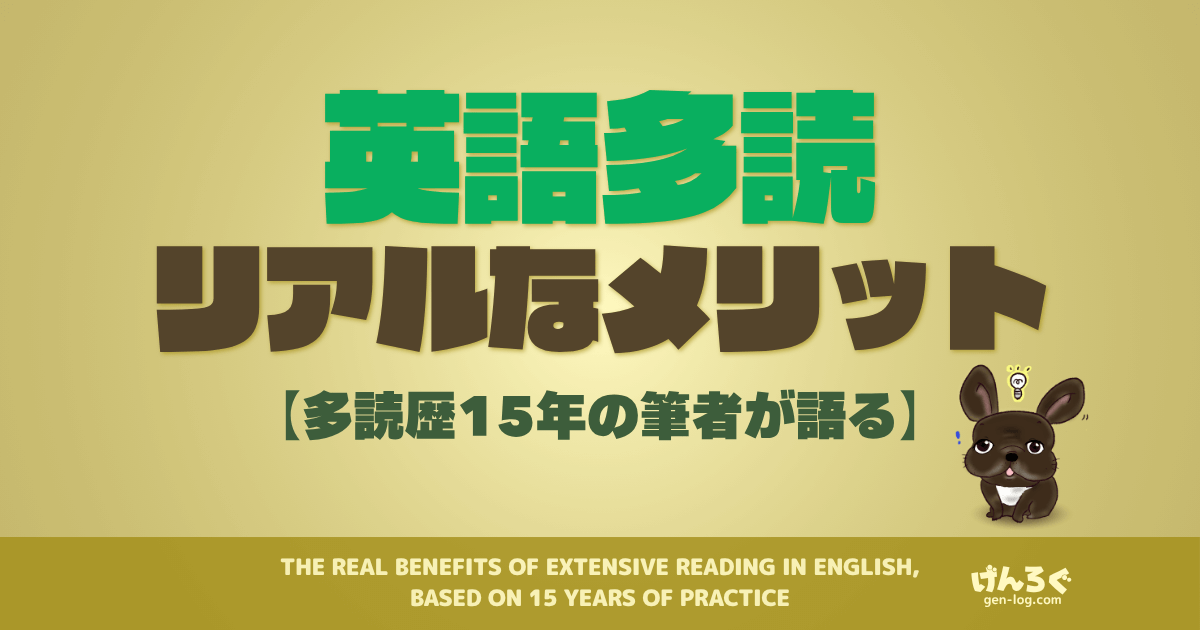英語多読は本当にやる意味あるのか?
これまでは一部の洋書好きにしか知られていなかった多読ですが、近年、
なにやら多読というのが良いらしいぞ…
というムーブメントが一般の英語学習者の人たちの中にも起こり始め、にわかにトレンドとなってきています。
しかし、わからないところは飛ばしてどんどん読み進めるという手法のため、
- 多読をやるメリットはあるのか?
- 多読をやるのは時間の無駄ではないのか?
- 精読や暗記をコツコツ続けた方がいいのではないのか?
と、不安に思っている人もいるかと思います。
しかし、多読には様々なメリットがあり、英語力向上に必要な要素ほぼ全てをカバーしていると言っても過言ではないほど、とても万能な学習方法です。
一方で、多読の弱点となりうるデメリットもいくつか存在しています。
そこで、今回お話しするテーマがこちら、
- 英語多読を行うメリット
- 英語多読を行うデメリット
それでは、始めていきましょう。
英語多読を行うメリット
多読にはどんなメリットがあるのでしょうか?
ポイントは5つ
- 量を稼げる
- 唯一の能動的インプット学習
- 未知語を認識できる
- 単純に楽しい
- 素材が選びやすい
多読には他にも様々な効用がありますが、特に重要だと思うメリットを5つ紹介します。
量を稼げる
なんといっても、多読の一番のメリットは量を稼げるということです。
多読を行う際の基本的なルールとして、
- 辞書を引かない
- 返り読みをしない
- 完璧な理解を求めない
というものがあります。
このルールのおかげで、罪悪感を感じずにどんどん読み進めることができ、精読では実現できないスピードで大量の英語を吸収することができます。
それでも、最初は読み進めるのにかなり時間がかかるかと思いますが、慣れるとスイスイ進めるようになり、1ページあたりの負荷がかなり軽くなるため、結果的にボリュームを効率よく稼げるようになります。

唯一の能動的インプット学習
大量のインプットが可能な方法は他にも、
- Podcastなどでの多聴
- 映画・海外ドラマでの多観
- その他海外ラジオなどでのながら聴き(聞き流し)
など、いくつかありますが、その中でも効果が一番高いのは多読という実感があります。
なぜかというと、多聴・多観が内容に集中していなくてもストーリーが展開していく受動的な学習方法なのに対し、多読は自分の意思で読み進める必要がある能動的な学習方法であるため、
常に一定の集中力をキープしなければ進めない
という特徴があります。
この制約が、多読が他のインプット学習と一線を画すところであり、最大のアドバンテージです。
未知語を認識できる
英語を文字情報でインプットすることによって、未知語を一つの単語として認識することができます。
つまり、知らない単語に対して、
この単語の意味は知らないが、この単語を一つの単語として認識している
といった感覚を持てるようになるということです。
リスニングで未知語に出会った場合だと、リンキングやリダクションも相まって、リーディングに比べて単語単位での認識が困難です。
また、音でしか単語を認識できないので、スペルは想像するしかありません。
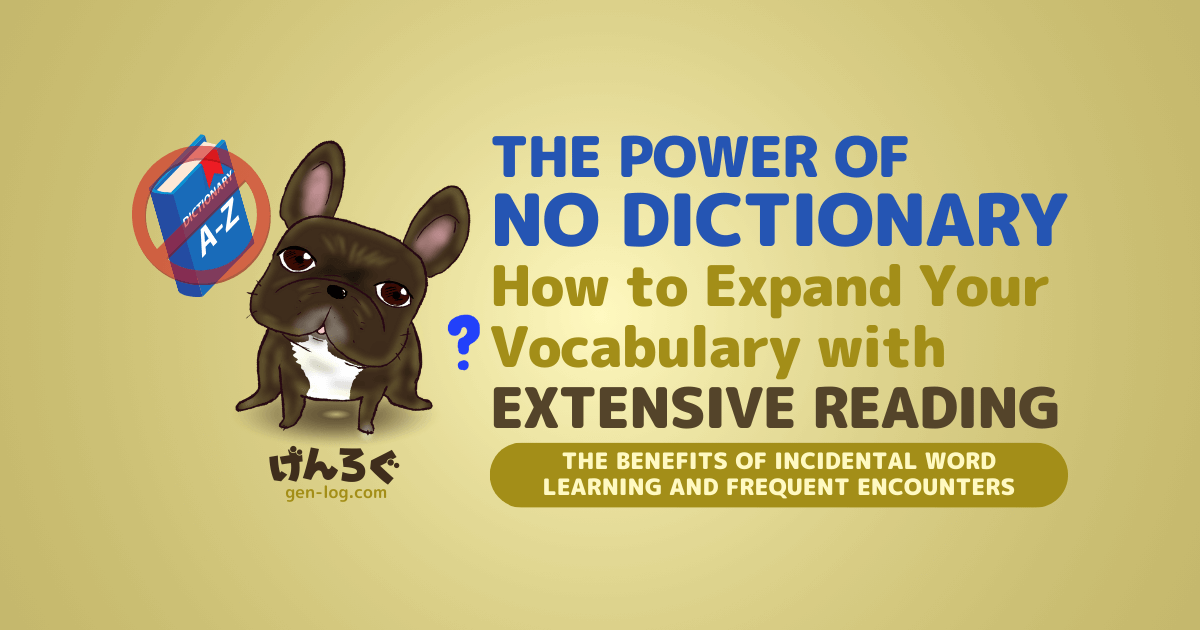
単語の出現頻度が上がる
小説やビジネス書は、あるテーマに沿って書かれているので、必然的にそのトピックに関連したワードが頻出します。
多読では、未知語はとりあえず飛ばすというルールですが、何度も同じ単語や表現に出くわすと、
 えいじ
えいじこの単語また出てきたな
と、さすがに認識するようになり、そのうちスペルも覚えてしまいます。
違う文脈でその単語に何度も出会っていると、意味はわからなくても、
- ポジティブ/ネガティブ
- 軟らかい/硬い
- 褒めている/けなしている
といった、なんとなくの情緒的な感覚が伴ってきますので、コアイメージを掴みやすくなります。
この感覚が使える英語を会得する上でとても重要になります。
近いテーマや同じ著者の本を読んでいると、似たような単語や表現が何度も出てくるので、効率よく語彙を定着させることができます。
初めのうちは関連性のある本をどんどん読んでいくといいでしょう。
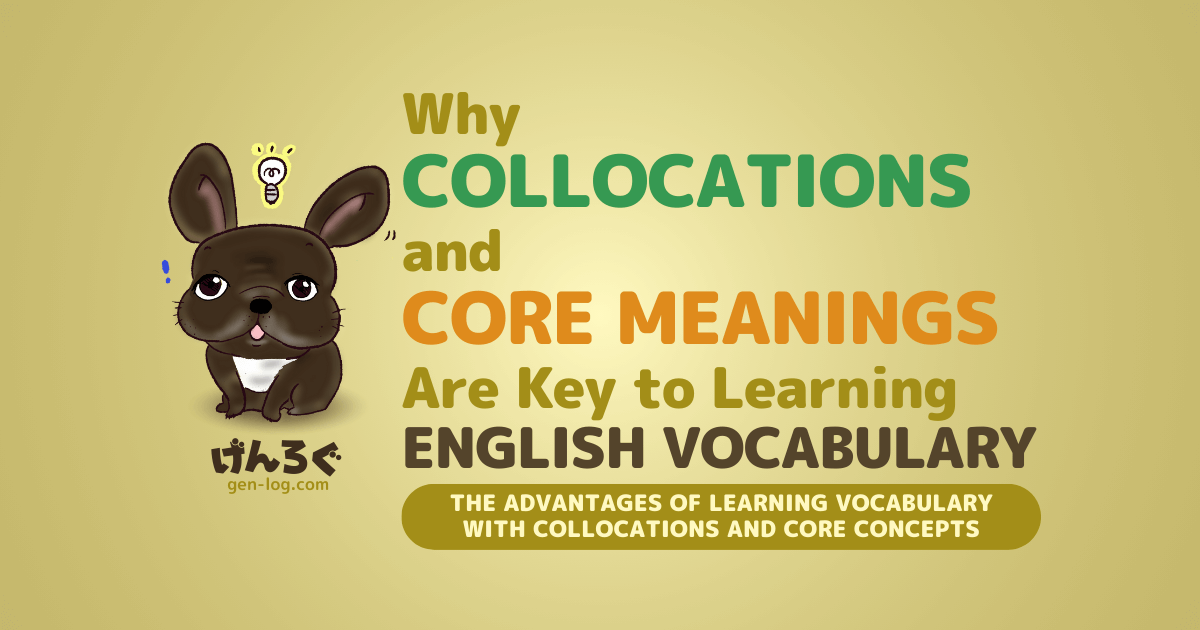
単純に楽しい
小説やビジネス書などの書籍は、文章のプロが何度も校正を重ねて、ようやく完成させた1冊です。
平易な英語で書かれていたとしても、読者を惹きつけるよう構成や展開を練りに練っていますので、文章が非常に洗練されています。
さらに、自分の好きなものや、興味のあるテーマのものであれば、なおさらページを進める手が止まりません。
そのうち「英語の勉強をしている」という感覚はなくなり、
知りたい情報や読みたいストーリーがたまたま英語だっただけ
という状態になり、単純に内容を楽しんでいる自分に気が付きます。
 げん丸
げん丸ここからが真のTadokistブヒな!
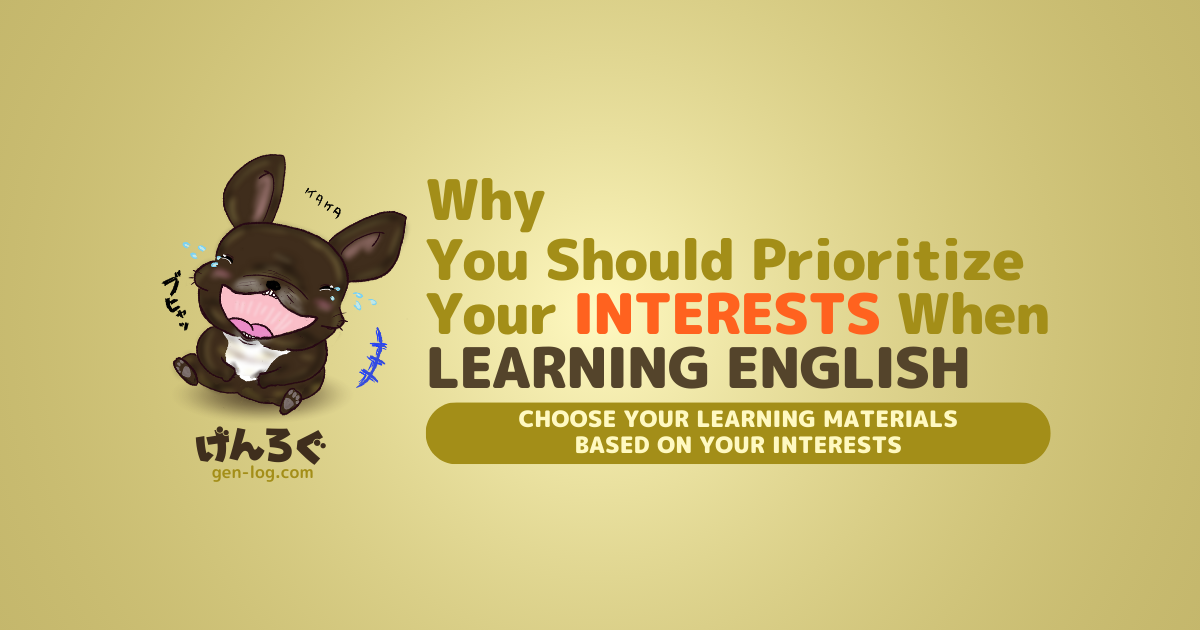
素材が選びやすい
日本では英語学習の人気が比較的高く、毎年様々な英語関連の書籍やテキストが出版されています。
正確な数字は把握していませんが、多く見積もっても年に数百冊くらいはあるのではないでしょうか。
この数字を多いと捉えるか少ないと捉えるかは、個人の感覚によるところかと思いますが、「英語の勉強」をするには困らない数字かと思います。
では、英語で書かれている書籍は年間何冊くらい出版されているのでしょうか?
スクロールできますhttps://wordsrated.com/number-of-books-published-per-year-2021/
Rank Country Year Number of titles Notes #1 China 2013 444,000 New titles and re-editions #2 United States 2013 304,912 New titles and re-editions #3 United Kingdom 2020 186,000 #4 Japan 2017 139,078 New titles and re-editions #5 Indonesia 2020 135,081 #6 Italy 2020 125,948 #7 Russia 2019 115,171 #8 France 2018 106,799 #9 Iran 2018 102,691 New and revised #10 Germany 2013 93,600 New titles and re-editions Number of books published each year per country
こちらのサイトのデータによると、アメリカだけで年間30万冊近くの書籍が出版されています。
その他の英語圏の国の出版数も加味すると、年間50万冊以上は出版されているのではないでしょうか。
 げん丸
げん丸桁が全然違うブヒな!
当然、母数が多いということは、それだけ、
- 良書に出会う確率が上がる
- どんなにニッチな分野の本でも探せば見つかる
ということです。
英語を生涯学習と捉えた時に、洋書多読であれば一生素材選びに困ることはありません。
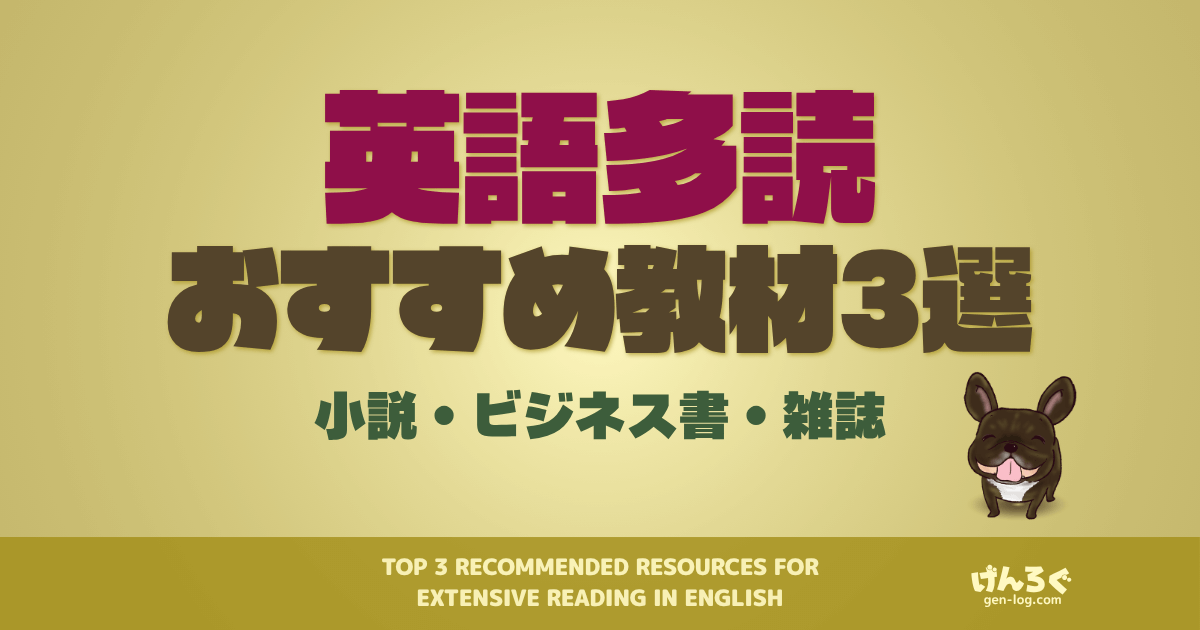
英語多読を行うデメリット
多読を行うデメリットはあるのでしょうか?
ポイントは3つ
- ボキャブラリーの増えるペースが緩やか
- 何となく読む癖がついてしまう
- 洋書は高額
多読は最も効果のある英語学習のひとつですが、いくつか弱点となりうるデメリットも存在しています。
くわしく解説していきます。
ボキャブラリーの増えるペースが緩やか
多読では、知らない単語は飛ばして読むというルールがありますので、どうしてもボキャブラリーが増えるスピードは遅くなります。
普段からボキャビルを英語学習に取り入れていて、1日に10〜20個の単語を暗記している
というような人は、不安に感じるかもしれません。
しかし、短期間で覚えた単語は短期間で忘れやすいという傾向があり、どんなに頑張って暗記をしても、実際に使いたい場面で出てこないということが多々あります。
一方、多読では重要な単語は何度も出てくるので、
その単語がどのような文脈の中で使われるのか
ということを、じっくり時間を掛けて、自然な感覚で覚えていくため、記憶の定着がまるで違います。
長期的なスパンで見ると、単語帳での暗記よりも、多読で身についたボキャブラリーの方が実際に使える単語(アクティブワード)の数は多くなります。
したがって、一見デメリットのように見えますが、実質的にはメリットになっているという側面もあります。
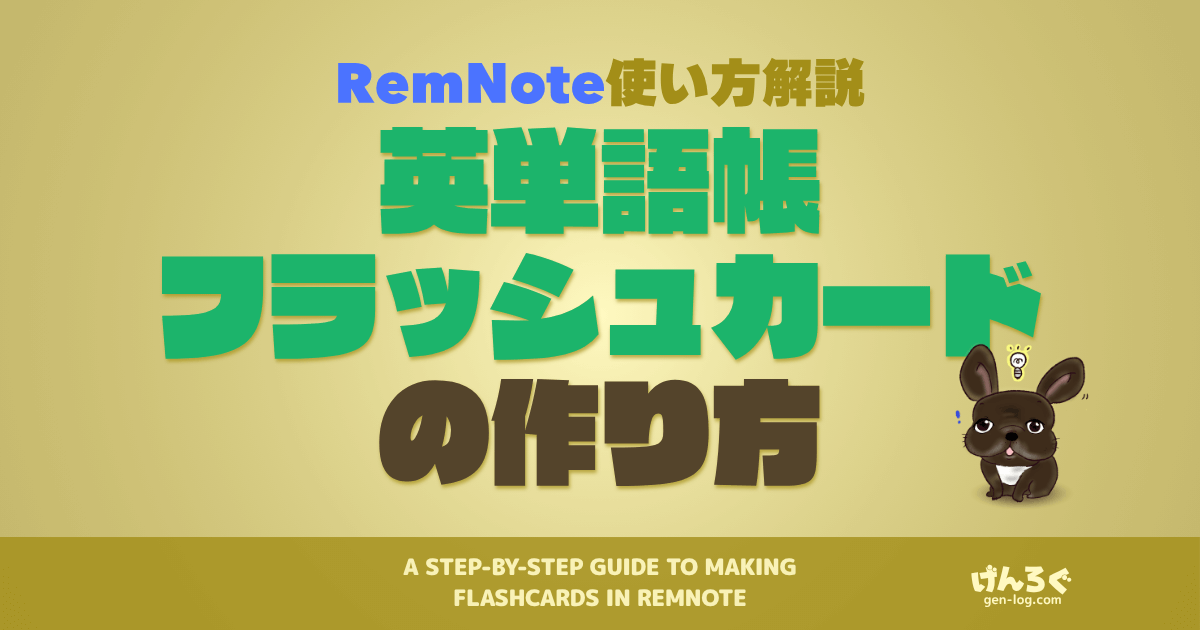
何となく読む癖がついてしまう
多読では、100%の理解は求めず、リズムやテンポを重視して読み進めていきますが、このルールを履き違えてしまうと、
ただ単に文字を追うだけで内容が全然入っていない
という状態になってしまいます。
このルールの意図は、
- 「細かいところは気にせずサクサク読み進める」=「集中しないでサラサラ読む」
ではなく、
- 「細かいところは気にせずサクサク読み進める」=「いちいち中断しないので集中力をキープできる」
というのが正しい認識です。
どうしても集中力が続かないという人は、適度に精読も取り入れましょう。
精読を定期的に行うことによって、多読を行った時でも、ある程度精読的な読み方ができるようになります。
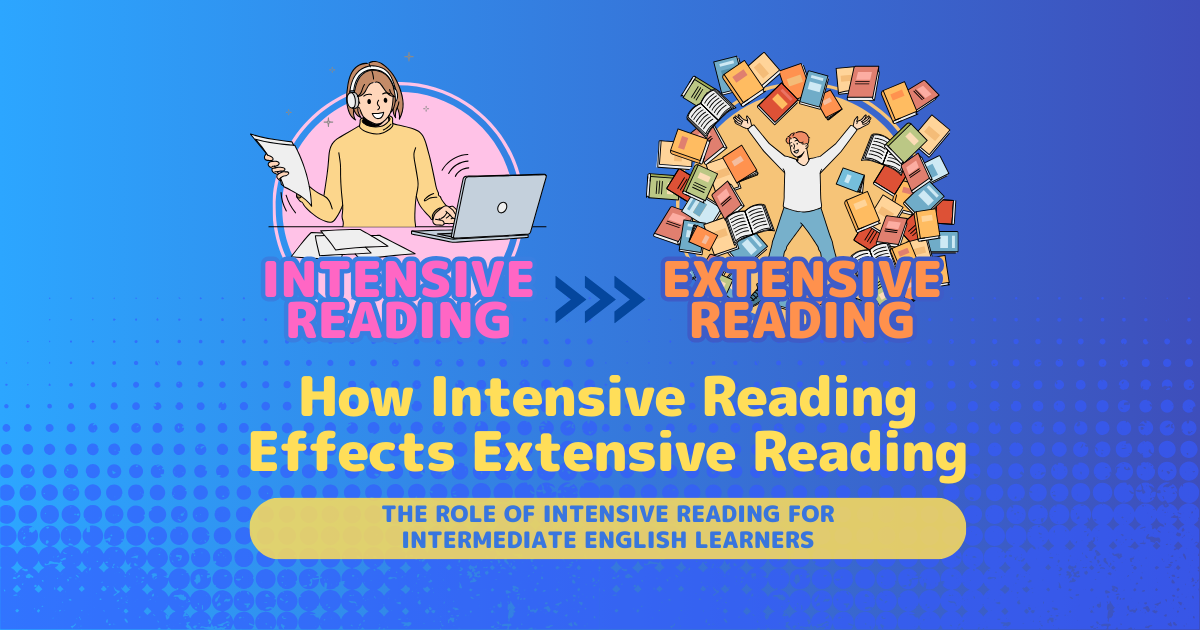
洋書は高額
一般的に見て、日本での洋書の需要は極めて低く、取り扱っている店舗が限られているため、どうしても流通価格が高くなりがちです。
少しでもコストを抑えたいという人は、電子書籍での購入をお勧めします。
さらに、
とにかくコストを抑えて洋書をガンガン読みまくりたい!
という人は、月額980円で対象の作品が読み放題のKindle Unlimited一択になります。
ただ、高いと言っても「その他の書籍と比較して」ということです。
洋書一冊読み終えるのに1ヶ月程度はかかるので、多読を一つの英語学習と捉えれば、かなりコスパがいい方だと思います。
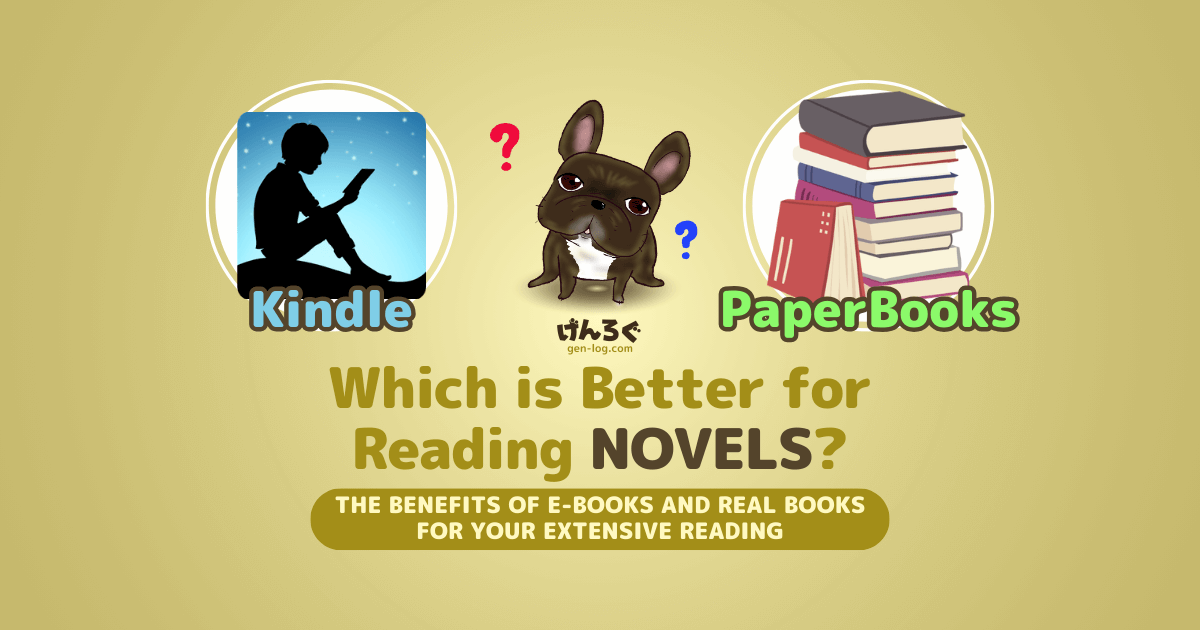
おすすめNo.1
英語学習アプリのご紹介
フランス発の洗練されたUI
🇫🇷 Made in France 🇫🇷
\すべて英語で展開されるから没入度が違う!/
漫画を読むように多読多聴できる|AIがあなたのレッスンを構成
15日間の無料トライアル実施中
※無料体験期間中のクレジットカード登録不要
※トライアル終了後の自動更新なし
おわりに

今回、英語多読のメリットとデメリットということで紹介しましたが、実際デメリットらしいデメリットは見当たりません。
むしろ、総合的に見て、実はメリットになっていることばかりです。
効果 × 楽しさ × コスパ = 英語多読
こう断言できるくらい、英語多読は最高最善の英語学習だと信じています。
気軽に始められて、時には休憩して、気が向いたらいつでも再開できる
洋書多読は確実にあなたの人生を豊かにしてくれると信じています。
それではまた、次の記事でお会いしましょう。
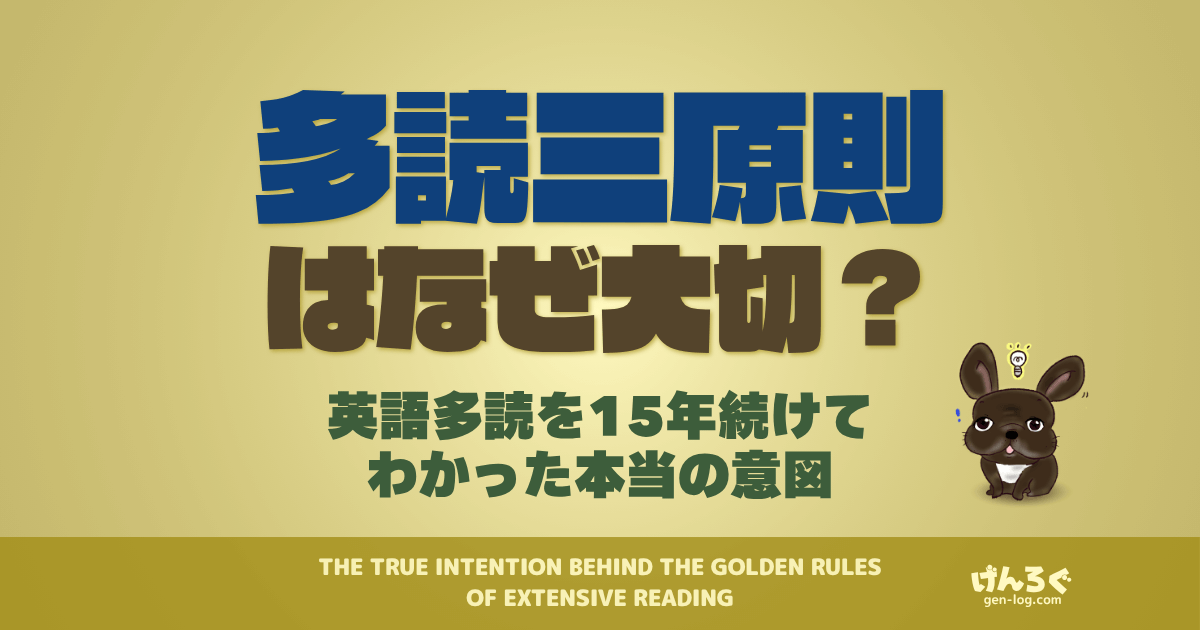
洋書多読を始めてみたいけど、
何から読んでいいかわからない…
そんな人におすすめなのが、Amazonが提供するサブスクプラン、
 げん丸
げん丸月額980円で対象の本が読み放題!
100万冊以上という圧倒的な数の洋書を取り揃えており、合わないと思ったらどんどん次の本にいくことができるので、多読と非常に相性が良いです。
月に1冊しか読まなかったとしても、通常購入するよりも安い場合がほとんどなので、月に1冊は確実に読むという人にとってはお得でしかありません。
現在、月額無料キャンペーンを行なっており、いつでも解約可能なので、洋書多読をノーリスクで試せるチャンスです。
まずは何冊か試しに読んでみて、洋書多読が自分に合っているかどうか確かめてみましょう。
\200万冊以上の洋書・和書が読み放題!/
お得な2ヶ月お試しプラン(499円)もあります。